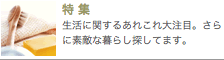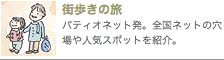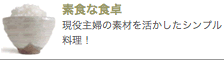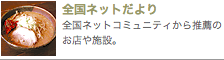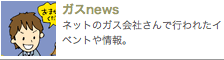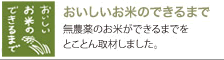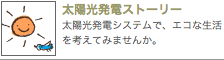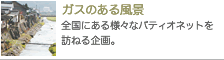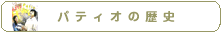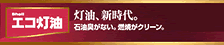>> トップページ >> 特集トップページ >> 2012年

優れた道具の洋服ブラシ
暮らしの中で絶対に必要な道具ではないかもしれない。
けれど、暮らしを豊かに、快適にしてくれる優れた道具だと思います。
寒くなるこれからの季節に恋しくなるのがウールやカシミアなどの衣類。もちろん外出にはコートやマフラーも欠かせないですね。でも、しばらく着ていると毛玉ができたり、濃い色のコートなんかはホコリも目立ってきたりします。「しょうがないか。」とワンシーズン我慢したり、頻繁にクリーニングに出したりしていませんか?
最近は洋服が安くなったので、「毛玉が付いたらワンシーズンで買い替える。」という方も多いかもしれません。でもちょっと待って! その洋服、お手入れ次第で長く着られるとしたら…。気になりませんか?
洋服をケアするブラシ
一昔前は、スーツといえば仕立てるのが当たり前で、一着がとても高価なものでした。そんな憧れのスーツを仕立てたからには、手入れもきちんとしたいのが人情。着た後は、丁寧に洋服ブラシで整えて仕舞う。これが良い物を良い状態で長く着るコツだったのです。近年また物を大切にと考える風潮になり、手入れをして良い物を長く使うという方も増えています。そんな中で『洋服ブラシ』が、優れた道具として見直されています。
ホコリを取るだけじゃない?
東京都足立区にある創業70年の老舗『(有)平野刷毛製作所』は、洋服ブラシからヘアブラシ、歯ブラシなど、あらゆるブラシを取り揃えた専門店です。全国のデパートで定期的に『ブラシの平野』というブランドで実演販売もされています。その平野聡士さんに『洋服ブラシ』について教えていただきました。
「洋服にゴミが付いている状態は、服地の繊維にホコリが絡みついている状態なんです。その絡んだ繊維をほぐし、一定方向に払うようにブラッシングするとホコリが取れて、だんだんと目が整ってきます。表面が整えば、ホコリが付きにくくなって洋服に光沢も出てきますよ。」と語る平野さん。ブラシをかける前と後で比べると、その艶の違いは一目でわかるほどです。
職人さんが手植えするブラシ
手植えブラシには、手軽に使える羽子板型と手のひら全体でつかめる水雷型があります。それぞれ土台になる木部には、植毛穴が羽子板型で122個、水雷型では233個、木工職人により中央から放射状に穴が空けられます。その後、熟練職人の手で一穴ずつ植毛されていきます。機械植えとの違いは、植毛穴の引き線(針金)が一筆書きのように全て繋がっていること。手間も時間もかかりますが、機械植えに比べて丈夫で、長期間の使用に耐えるブラシが出来上がります。

1.一穴ずつ針金で植毛するので、手間がかかるが丈夫な洋服ブラシが仕上がる。2.放射線状にブラシの穴を開けていく。実はこの作業がブラシの基礎となるので熟練の技術を要する。3.竹ひごを挿すときれいに放射線状に広がる。4.足踏みペダル式の穴開け機械は相当な年代物。穴を開ける「きり」はオリジナルの特注。5.〜6.長い馬の本毛を半分に折り曲げて植毛。7.引き線をならして真鍮釘で蓋をする。8.バリカンで毛を55ミリにカットする。
やわらかい馬毛
来は天然毛洋服ブラシといえば豚毛でしたが、近年はカシミアやアンゴラなどデリケートな洋服が増え、豚毛よりもやわらかい馬毛の洋服ブラシが主流になっています。また天然毛は、静電気が起こりにくいのも特長です。
『ブラシの平野』の手植え洋服ブラシは、毛足が長く55ミリもありきめが細かく、程良いコシが特長です。植毛時には毛を半分に折り曲げるので、全長約13センチの長い厳選された本毛を使います。本毛とは、馬の尾毛の中で最も太く長い毛で一頭の馬からほんの僅かしか取れないほど貴重なものです。
毛玉取りと洋服ブラシ
どうしても出来てしまう毛玉。冬に着たいウールやカシミアの洋服には常につきまとう問題です。「毛玉取り器や毛玉取りブラシがある。」と思いがちですが、実は、毛玉って繊維がよれて絡まった状態なんです。毛玉取り器などで毛玉を切り取ってしまうと、服地が減って薄くなってしまいます。
その点、洋服ブラシなら、絡まった繊維をほぐして目を整えるので、繊維が減らず洋服が長持ち、さらに艶もでます。大切な洋服は、ブラシでケアするのがお薦めです。暮らしの中には様々なブラシがありますが、洋服ブラシを使って気に入った服を長く気持ちよく着られるっていいと思いませんか?

9.ハサミで丁寧に整えて仕上げる。10.羽子板型の洋服ブラシが完成です。11.植毛穴を裏から見ると引き線(針金)がすべて繋がっている。12.手入れは金クシで。こまめな掃除がコツ。13.平野聡士さん(右)と職人の森さん(左)。

日本の文化「漆器」
食事のときに器を手に持ったり、口を付けて食べる国って珍しいそうです。
熱を伝えにくい漆器は日本人の食文化にぴったりの理にかなった器なんですね。
みなさんにとって「漆器」とは、どんなイメージでしょうか? 年に数回、お正月など特別な時に使う器?高価だから用心深く扱わないといけないし、手入れが面倒くさそう?そんな印象を持っている方は結構多いのではないでしょうか。 実際、塗り物は高価なのですが、職人さんがどれだけ手をかけて作り出しているかを知ると、価格にも納得できたり、使ってみたいなと感じてくるかもしれませんよ。
天然の塗料「漆」の不思議
漆は漆の木から採れる天然の塗料です。その特性は不思議なもので、空気中の湿度を取り込んで酸化させることで固まります。だから乾かすときは、湿度が60〜70%くらいあるのがベストなんです。塗り終えた後は、8時間ほどかけてゆっくりと乾かしていきますが、実は漆が本当に乾ききるまでは、十年とも百年とも言われていて、その間、漆はずっと「生きている」んです。
何年もかかって乾くから、漆は強度があって丈夫。例えば、ニスとか接着剤とか早く乾くものは、乾ききると強度がなくなるので、割れたり剥がれたりしますよね。その点、漆はゆっくりじっくり乾いていくので、丈夫で永く使い続けることができるんです。
気軽に普段使いする漆器
宮城県の鳴子といえば鳴子温泉があり、鳴子漆器が特産の町です。今回はその鳴子で工房兼ギャラリーを営んでいる漆塗り職人の佐藤建夫さんにお話しを伺いました。
「漆器って難しいわ。扱うのが怖い。と言う方がいますが、器だから、弱ってきたり壊れてしまったら修理すればいい。漆器ってメンテナンスができるんですよ。使う前から心配しないで、気軽に使ってあげればいいんです。」と佐藤さんはニコニコ笑顔で教えてくれました。
漆器は縄文時代から使われてきた日本の文化。そんな昔のものが現代も受け継いで作られ続けているのは、やっぱり漆器って、使っていて心地が良いからなのでしょう。特別な時にだけ使う漆器もあると思うけれど、ちょっと贅沢にお気に入りを普段使いしてみたらいかがでしょう。 毎日の食卓で、ふとしたときに見る器が素敵だったら、ちょっと嬉しくなりませんか?

1.漆塗りの工程は木地の表面を滑らかに削る「木地調整」→生漆を一度塗る「木固め」(研ぎ)→「下地」(研ぎ)→漆を塗り始める「中塗り」(研ぎ)2回繰り返す→最後に厚めに漆を塗る「上塗り」で仕上がる。約3ヶ月くらい掛かってやっと完成する。「中塗り」をする佐藤建夫さん。2.漆塗りの刷毛には女性の髪の毛が使われる。3.漆を漉す道具。
育てる器
漆器は年月が経つほど、漆の透明度が増して艶がでてきます。使い終えた後は、ちゃんと洗って水気をふきんで拭き取ること。少し手間はかかるけれど、愛おしくなるほど綺麗に育っていく器は他にないのではないかと思うのです。
良い漆器の選び方
最近では、千円くらいの漆塗りのお椀が売られていたりもしますが、高価な漆器には、もちろん理由があって、それは良い漆器の選び方にも繋がります。「一番は手でしっかり持った時に、手触りが良く、しっとり手に馴染むもの。持った時に柔らかく感じるものが自分に合っている漆器です。」と佐藤さん。「手に馴染む」「柔らかいと感じる」ことは、漆を塗る前の木地の調整や下地塗りがしっかりされているし、角を丸く研いで丁寧に作られているから。きちんと手をかけ、時間をかけて作られているものは、使うときも心地良いものです。

4〜5.ヘラを削り整え下地を塗る。一面ずつ塗っては乾かすのを繰り返す。6〜7.刷毛を削って先端をとがらせる。8.和紙に漆を包んで細かなゴミを漉す。9.佐藤さんは1日100個くらい漆を塗るそうです。10.むろで漆を乾かす。11.ギャラリーも見応えあり。12.艶やかで美しい漆器。13.佐藤さんと愛犬ななちゃん。漆の体験教室も行っています。
漆塗りの難しさ
漆塗りの職人として46年になるベテランの佐藤さんでも、漆には勝てないと語ります。「自然の塗料だから、頭で描いているような色が出なかったり、湿度が高すぎても低すぎてもダメ。納得できるものが出来た時は、本当に嬉しい。けれど、同じように手をかけたのに乾燥でイメージした色にならないと、まだまだだなと思います。だから人の思いで自在に使うというより、漆に使われている感じかな? 漆に『これでいいが?』と問いながら日々作っています。」 どんなに技術があっても、漆には(自然には)勝てないのだと語る佐藤さんが印象深く、職人の謙虚さが伝わってきました。

伝統を受け継ぐ扇子
ひとつの扇子を作り上げるには、幾人もの職人さんの技術が必要です。
扇子の土台となる「扇骨」は、職人技が光ります。
私たちの暮らしの中で、儀式やお祭りで使われてきた扇子。または涼むための道具としても身近な存在です。扇子には実用的な夏扇から舞扇、茶席扇、飾り扇などたくさんの種類があります。
最近は、百円ショップなどでも売られていますが、実は扇子は伝統工芸品。「扇骨」と呼ばれる扇子の骨の部分だけでも制作工程が34もあるんです。昔から扇骨の産地として知られる滋賀県高島市安曇川町では、全国の9割を生産していて「高島扇骨」と呼ばれています。
扇骨は左と右の外側にある2枚が「親骨」で作るのに18工程、内側を「仲骨」といい16工程必要で、合わせて34工程になります。複雑で時間も掛かる扇骨作りは、幾人もの職人さんが分業で仕上げていきます。
出来上がった扇骨の約8割が京都へ出荷され、京扇子として販売されます。扇子というと京都で作られているように思われますが、土台となる扇骨は滋賀県で作られ、京都で紙を貼り京扇子に仕上げます。東京で仕上げれば江戸扇子になります。仕上げる場所で扇子の名称が変わるのも面白いですね。そんな高島扇骨を使って滋賀県でも「近江扇子」という素敵な扇子を作っています。
良い扇子ってどんな扇子?
安曇川町で近江扇子の製造直売も行い、職人でもある「すいた扇子」の吹田政雄さんを取材させていただきました。親子二代で80年も扇骨を作り続けている吹田さんに、良い扇子はどんな扇子ですか?と伺うと「新しい扇子は開きにくいでしょう? それが本当に良い扇子ですよ。」と教えてくださいました。扇子を閉じると親骨が滑らかに曲がっていて、ピシッと締まります。最初は開きにくくても、長く使っていると手に馴染んで使いやすくなるので、開きにくいくらいの物がよいのだそうです。
長く使うと竹にツヤも出て、手に吸い付くような扇子に育ってきます。そんな愛着を持って使える扇子を1本は持ちたいものですね。
肝心要の「要」です
最近は中国製の扇骨を扱う業者も多くなっていて、京扇子の中にも増えているのだとか。
「中国の技術も年々上手くなっていますが、私たち職人が見ると細かな部分の職人技がないので、すぐに分かります。」と吹田さん。見た目が同じように見える扇子でも、比べて説明していただくとよく分かりました。(上記写真7〜8参照)中でも、重要な部分が「要」の工程です。高島扇骨は、棒状のセルロイドを差し込み、熱した金バサミで両側から押さえて留めます。
一方、中国製は片側が玉になったプラスチックの棒を差し込み、もう片方を熱で溶かして留めます。一見、仕上がりは同じように見えますが、仰いでみると一目瞭然。中国製の方は、仰いでいると留め具が緩んでいる感じで、ぐらぐらしています。ガタついて「要」がポキッと折れて取れてしまうことも多いらしく、「すいた扇子」さんに修理の依頼が来ることもよくあるそうです。
扇子の「要」は『肝心要』の語源とも言われているので、確かな物を選びたいですね。

1.1300本の仲骨を板状にして削る職人技。吹田さんが行うのは一番最後に削って形を整える「締直し」という作業。2.天日に干して竹の青味を抜く作業「白干し」。安曇川町の風物詩です。3.均一な扇骨ができあがる。
伝統の技術を守る人々
300年もの伝統を守り続けてきた高島扇骨ですが、エアコンや扇風機などの出現、中国の安くて大量に作られる扇骨に押され、年々、生産量が減ってきています。
その影響で、京都にある扇子店や百貨店で取り扱う京扇子の中にも、中国製の扇骨が使われているものが多くなっているそうです。
「そんな中、日本の伝統技術を守るために、絶対に滋賀の扇骨を使って頑張る。と言ってくれている京都の扇子店が3軒あるんです。安い物が良いと言われると勝てないけれど、日本の伝統技術も見てほしい。」と吹田さんは熱く語ります。
良い物を長く使うことが愛着であり、暮らしに潤いを与え、伝統も守れるのではないかと思います。
今年の夏は、ぜひ「良い扇子」を探してみてはいかがでしょう。

4.材料の竹の9割以上が廃材となります。5.毎日たくさんの扇骨を仕上げます。6.庖丁と呼ばれる独特の道具。7〜8.右)中国製、左)高島扇骨。右は親骨の磨き作業をしていないのでツヤがない。閉じた時も扇骨がデコボコしている。9〜10.奥様。親骨と仲骨の枚数を合わせ、濃い色から薄い色へグラデーションになるよう並べかえる。11.要を付ける。12.すいた扇子さん店内。13.様々な扇子が揃います。14.閉じた姿もきれい。15.組合の理事も務める吹田政雄さん。

職人技の砂時計
砂時計は、職人さんがひとつずつ
ガラスを吹いて手作業で作っているんです。
どこか心惹かれる砂時計の魅力が
ここにありました。
かつては、様々な場所で使われていた砂時計。調理時間を計ったり、学校の授業でも使われたりと、懐かしい記憶が思い浮かびます。しかし現在は、キッチンタイマーなどが普及したことで砂時計を見かける機会は、すっかり減ってしまいました。
砂時計の形状は、大きく分けると、ぷっくり膨らんだひょうたん型と真っ直ぐのシリンダーのような形とがあります。特に制作に手間が掛かる方がひょうたん型です。今では、ひょうたん型の砂時計を作れる職人さんは、日本に3人しかいないと伺いました。そのお一人である東京硝子工芸の金子治郎さんに今回、取材をさせていただきました。
取材をする中で、砂時計の制作は、すべてが手作業であることを知り驚きました。職人さんがひとつひとつ丁寧にガラスを吹いて作っています。何でも機械化になっているこの時代に、砂時計は職人さんの技術によって作られています。そこにとても温もりを感じました。
「手作業でなければ出せない繊細な形が砂時計の持ち味なんですよ。」と語る金子さん。職人技の美しい砂時計が毎日の生活にあると、ホッとする時間ができて温かい気持ちになれますね。

砂時計職人のきっかけ
東京都葛飾区で45年、砂時計を作り続けている金子さん。金子さんのお父さんはガラス工場の社長であり、ガラス職人でした。当時は、理化学用のガラス機器や薬液を入れるアンプルの制作をされていたそうです。しかし、そのうちに機械技術が向上し、半自動でアンプルの制作ができるようになると、葛飾周辺のガラス工場や職人さんはどんどん去っていきました。
そんな折り、貿易会社からの依頼で輸出用の3分間のエッグタイマーを制作したのが、砂時計を作り始めたきっかけです。金子さんは、忙しいお父さんの手伝いをしているうちに、18才から砂時計を作りはじめました。
一番難しい「蜂の腰」
制作工程の中で一番難しい作業は、砂時計の命でもある「蜂の腰」と呼ばれる砂の通り道です。炎で加熱されたガラス管は、みるみるうちにくびれていきます。素早く息を吹き入れながら直径をどんどん細めて調整します。砂の通る直径は、1ミリ以下。でも細すぎてもだめです。長年の職人の勘で仕上げられます。

1.工房で砂時計を作る金子治郎さん。2.長いガラス管をバーナーで熱して、細長く伸ばした後、均等な大きさで切り分けます。3.砂を振るいにかけ粒子の大きさを揃えます。4〜5.ジリコンサンドや乾燥剤の砂など様々な種類があります。
砂の種類とこだわり
砂時計の砂は、基本的には砂鉄ですが、砂状のものなら大抵、砂時計にできるのだそうです。良く見かける青やピンクなどのカラフルな砂は、実は乾燥剤を細かく砂状にして着色したものです。
他にも金子さんは、自然砂、蓄光タイプの夜光砂、鋳物の型を取るための砂ジリコンサンドなど4種類の砂を扱っています。「砂時計用の道具自体が少ないから、無いものは自分で作らないといけないんですよ。ジリコンサンドの砂の色も染料を自分で調合して染めています。毎回同じ色に調合するのは大変だけどね。」と教えてくださいました。
砂によって使用用途が変わる
乾燥剤の砂は軽いので、高温の場所や熱が加わる所に置くと、砂時計内で空気が圧迫されて砂が落ちなくなってしまいます。だから、サウナにあるのは、重い砂鉄の砂時計なのです。
オーダーメイドの砂時計
東京硝子工芸では、砂時計職人さんだからできる砂時計のオーダーメイドも制作しています。 旅行に行った時の記念の砂や甲子園の土、大切なペットの遺骨まで、1つからオリジナルの砂時計を作ってもらえます。また、壊れてしまった記念の砂時計の修理も行っています。 暮らしの中で、アナログに時を刻む砂時計。落ちていく砂を眺めながら、リラックスする時間も時には必要ではないでしょうか。

6〜9.制作工程。常にガラス管を回しながら中心を熱して、くびれをを作っていきます。片方ずつ熱してガラスを吹きひょうたん型にしていきます。両方が膨らんだら「蜂の腰」を最後に仕上げます。10〜11.ガラスの片方を閉じ、砂を入れます。手作りの台に砂時計を並べ一斉に3分間計ります。余った砂は針金で真ん中の穴を塞ぎながら出し、最後にガラスを閉じます。15.できあがり!16.気さくに教えてくださった金子さん。

こだわりが作りあげる耳かき
耳かきは、さりげない存在ですが、
とっても奥深い世界がひろがっています。
種類やカタチや用途によって
驚くほど細かな工程がありました。
私たちの暮らしの中で、何気ない道具の中にも職人さんがこだわって作っているものがあります。例えば耳かき。耳かきを作る素材には、ステンレスやプラスチックなどの工業製品をはじめ、様々なものがありますが、昔から手で作られるものに竹があります。竹を素材に機械で作っている耳かきもありますが、竹細工職人がひとつひとつ丁寧に作った耳かきは、持った感触も良く、使用感が最高に心地良い耳かきに仕上がっています。何しろ竹自体が持っている、しなやかさと弾力性は、デリケートな耳の奥にも優しいのが特長です。
たくさんの用途に応える
「お客さんが、真剣に1本1本さじの部分の感触を手の甲で確かめて選んで買って行かれるんですよ。」とおっしゃるのは京都の二寧坂で竹細工店を営む三代目の神田智弘さん。なぜなら、耳かきのさじの部分だけでも種類と個性があるからです。さらに使うお客さんの好みも加わると多岐にわたり、奥深い耳かきの世界がひろがります。 まず、さじ部分の大きい小さいで、使う方々の好みが分かれます。また、さじ部分の曲がり具合で用途が分かれます。例をあげると、きつく曲がっていると「耳垢を取る」用に使い、曲がりがゆるいと「痒い部分をかく」用に使う。頻繁に耳かきを使う人は、さじの曲がりがゆるい方を使う方が多いそうです。
さらに、男性と女性の違いなのでしょうか。耳かきの柄の太さ形もそれぞれの好みに分かれます。非常に細かったり、横に平べったい形をした柄もあったりと様々です。ちょっとした耳かきと思いがちですが、個人の好みを追求していくと種々様々な耳かきの世界がひろがっているようです。
素材の竹による違い
その様な耳かきの好みを満足させてくれるのが、やはり昔から好まれている素材「竹」になります。竹にもいろいろと種類があります。今回、神田さんにお見せいただいた種類は「真竹」「虎竹」「煤竹」の3種類。「真竹」は、青い竹を油抜きして乾燥させた「白竹」の状態のものを使います。採れてからそれほど年数も経っていないので柔らかく、比較的耳あたりの良い耳かきといえます。「虎竹」は、虎のような模様がある竹です。柄の部分が広く平べったいのが特長です。「煤竹」は、囲炉裏の上などで長年燻された竹です。茶褐色で何とも味わい深い色をしており、この煤竹こそ最高級の耳かきになります。煤竹は、百年物、百五十年物と年数が経つほどに竹自体も貴重な耳かきとなります。囲炉裏などがない現代、この様な年代物の煤竹が手に入らないようになったそうです。

1.割った竹を剥いでいる作業中の三代目:光竹斎こと神田智弘さん。2.竹の種類。左から真竹。虎竹。煤竹(ひねりを加えたり、短くしたりと趣向を加えています)。一番右の3本は、最高級の煤竹耳かき。3〜4.耳かき作りの工程。5〜7.細かな耳かきを作っているところです。細心の注意を払い微妙に小刀を使っていきます。8.耳かきを作るにあたっての道具。伝統工芸の専用道具が大変美しい。
耳かきの様々な工程
さりげない存在の耳かきですが、ひとつの耳かきが出来るまで様々な工程があります。まず、素材の竹を割り、余分な肉を剥ぎます。さらに、さじになる部分を専用の道具で削り、熱を加えて曲げて、角張った耳かきのような形になります。それから小刀で丸みを付け、私たちが知っている耳かきの形に仕上げていきます。さじの部分は非常に小さいので、気を使う箇所です。耳かきの形になったら、今度は丁寧にペーパーをかけて仕上げていきます。このような細かな工程を経て、職人技と呼べる耳かきが出来上がります。
京都の伝統工芸
様々な伝統工芸が息づく京都。先々代から数えておよそ90年、竹細工店としてやってこられたのはひとえに「面倒くさがらずに、思ったことはやりとおすこと。」と、語る神田さん。この職人魂が、多くの人々の心を捉えていたと感じました。観光客の多い二寧坂で、竹の花かご作りから始まった神田竹細工店。数多くの竹細工を手がけながら、日本の伝統を引き継いでおられました。

9.二代目のお父様と三代目:光竹斎さん。10.さじの大きさや曲がりも様々。11〜15.花かご作りが出発点。粋な時計盤、御用達の花かご、お箸など竹細工もいろいろ。竹細工教室も行っています。4名から15名程度で一人2,500円。

職人さんが作る江戸木箸
箸は、人と食を繋ぐ命の箸渡しをする大切な道具。
だからこそ、握ってみて自分に合う箸を見つけてほしい。
私たちの暮らしの中に無くてはならない道具のひとつが箸です。箸は食べるための道具であり、生きるための道具でもあります。だから私たちの暮らしの中で、実はとっても重要な役割を果たしているのです。 「靴は履いてみて買うのに、なぜ箸は握ってみて買わないの?」という箸職人の竹田勝彦さんの言葉に衝撃を受けました。なぜなら、今まで使いやすさをそれほど重要だと思わずにいたからです。よく考えれば、足に個人差があるように、箸を使う手も人それぞれ。それなのに、箸は色や柄だけで選ぶことが多かったように思います。 大黒屋さんの江戸木箸を握ってみたときに、その握りやすさに「箸ってこんなに手に馴染むものなんだ!」とうれしくなりました。
使いやすい箸ってどんな箸?
今回お話しを伺ったのは、大黒屋のご主人で箸職人の竹田勝彦さん。店内にずらりと並ぶ箸は、200種類以上あり、すべて職人さんの手で作られています。 竹田さんに使いやすい箸とは?と聞くと、「握りやすくて、つまみやすい箸。」との答え。単純明快です。「本当に良い物は使ってみないとわからない。自分に合った良い物を選ぶにはたくさん比較しないと分からないでしょう? だから、使う人の身になって、そんな想いで作っています。」と気さくに応えてくださいました。素材が良い物、高価な物など『良い物』はたくさんありますが、例えば、とても素敵な洋服があっても、サイズが合っていなければ、その人にとっては着にくいし似合わない。だから『本当に良い物』とは言えません。自分の体に丁度良い物が『本当に良い物』なんです。
こだわり抜かれた江戸木箸
もともと食器問屋の営業マンだった竹田さんは「自分で使っている箸が使いづらくて、本当に使いやすい箸を作りたい!」という思いで20年ほど前に独学で箸職人に転身されました。
それまで箸といえば、断面が四角のものがほとんどでしたが、竹田さんは、箸は基本的に親指、人差し指、中指の3本で支えるから、角も奇数の方が持ちやすいに違いないと五角形の箸を考案しました。その後、2年をかけ七角という円周の360度を割り切れない角度の箸を作り上げました。機械では作り出せない、七角のバランスを職人の感覚だけで全く同じ形に作り上げていけるのは、まさに職人技。そして、角が指に触れないこの奇数の角の箸が不思議とピッタリ手に馴染むのです。

1.緊張感のある作業場の風景。分担作業ではなく、自分の作った箸は最後まで同じ職人さんが仕上げます。2.箸職人であり、社長の竹田勝彦さん。 3.左の2つが削る前の箸で右の2つが削った後の箸。角がきれいに出ています。
自分だけの箸探し
「良い箸を使うと食べ物も美味しくなるんだよ。」と語る竹田さん。小さな粒がスッと取れる、取りたい物がきちんとつまめる。そんな箸なら食べることに集中できます。つかみづらかったり、太すぎたり、細すぎたりすると、食べることよりも、つかむことに気を取られてしまいますからね。一般的に使いやすいとされる箸の長さは、手首から中指の先までの長さに3〜4センチプラスしたものです。そして「喰い先一寸」といわれる箸先3センチが、箸の最も重要な部分で、先が細い方が握る部分をあまり開かなくても箸先がピタッと合うので手が疲れないのだそうです。江戸木箸は、先端まで角がぴしっと入っていて、職人さんの魂が込められている部分なんです。
職人さんが想いを込めて手作業で作る箸は、使うたびに真剣な想いが伝わってくるようです。そしてどんな職人さんが作った箸なのか知ると、より一層愛着が湧いて大切に使いたくなりますね。
自分にとって使いやすい箸を見つけられたら、それは一生大切にしたいし、とても幸せなこと。箸の大切さを改めて知ることができました。

4〜7.箸の制作工程。目の粗いヤスリから細かいヤスリまで何度も磨き、感覚のみで角度を仕上げていきます。最後に箸の先端まで丁寧に磨き、仕上げカンナをかけ、摺り漆で木目が見えるように仕上げます。8.様々な角度を感覚だけで削っていく竹田さん。1本1本がほとんど同じに仕上がるのが職人技です。9.お店では握って選べるように箸がたくさん並んでいます。10.豆腐箸やらーめん箸、お茶漬丼箸などユニークな箸もいろいろ。